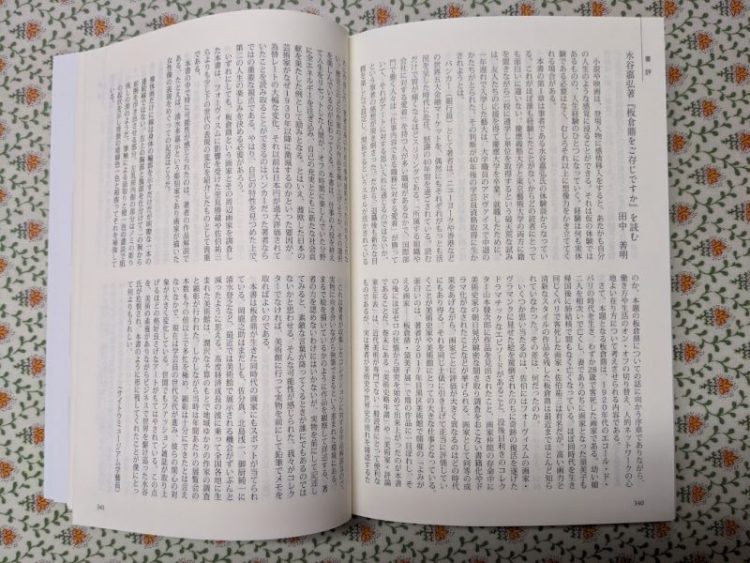小説や映画は、登場人物に感情移入すると、あたかも自分の人生のような感覚に浸ることができる。それは仮の体験ではあるものの、人生経験のひとつになっていく。経験は何も実体験である必要はなく、むしろそれ以上に想像力をかき立ててくれる場合がある。
本書の第1章は筆者である水谷嘉弘氏の体験談からなっている。これがほぼ誰も経験したことがないからどの読者にとっても面白いに違いない。慶応義塾大学と東京藝術大学の両方に籍を置きながら二校に通学し単位を取得するという破天荒な試みは、友人たちの応援を得て慶応大学を卒業。就職したために一年遅れで入学した藝大は、大学職員のアドヴァイスで中退のかたちがとられた。その判断が40年後の学芸員資格取得に生かされようとは。
バンカー(銀行員)として著者は、ニューヨークや香港などの世界五大金融マーケットを、偶然にもそれぞれがもっとも活況を呈した時代に赴任、怒濤の40年間を過ごされている。読むだけで胃が痛くなるほどスリリングである。「所属する組織や会社に対する愛着」を持つ人が多い職場があるなかで、国際部門で働く人々は「仕事内容である職務に対する愛着」が勝っていて、それがアートに対する思い入れに通じるのではないか、という筆者の感想が突き刺さった。だから、退職後も新たな目標を楽しんで設定し、開拓するというスキルが活かされているのか。本題の板倉鼎についての話に向かう序章でありながら、働き方や生活のオン・オフの切り替え、人的ネットワークの心地よい在り方について考えさせられる内容である。
さて、本題となる板倉鼎は、1920年代のエコール・ド・パリの時代を生き、わずか28歳で客死した画家である。幼い娘二人を相次いで亡くし、妻でありのちに画家となった須美子も帰国後に肺結核で間もなく亡くなっている。ほぼ同時代を生き同じくパリで客死した画家・佐伯祐三は有名だが、高い画力と清新なスタイルの作品を残した板倉鼎は最近までほとんど知られていなかった。その差は、何だったのか。
いくつか思い当たるのは、佐伯にはフォーヴィスム画家・ヴラマンクに見せた絵を罵倒されたのちに奇跡の復活を遂げたドラマチックなエピソードがあること、没後目利きのコレクター山本發次郎に作品を見出されたこと、画家仲間の存命中に美術史家の朝日晃が綿密な聞き取り調査をおこない書籍化やドラマ化されたことなどが挙げられる。画家として同等の成果をあげながら、画家ごとに評価が大きく異なるのはどの時代にもあり得る。それを同じ土俵に引き上げて正当に評価していくことが美術史家や美術館にとっての大きな仕事となっている。面白いのは、著者が2017年目黒区美術館で開催の「よみがえる画家-板倉鼎・須美子展」で鼎の作品に一目ぼれし、その後にほぼゼロの状態から研究を始めて出来上がったのが本書であることだ。巻末にある「美術史略年譜」や「美術家・評論家生年表」は、近代美術が専門でない一般読者にとって便利なものであるが、実は著者が美術史や世界史の流れを確認するために作成した、著者自身のための参考資料だったのかもしれない。歴史上のどの作家のどの作品を救い上げようか、その選択を楽しんでいるのが伝わってくる。本書は、仕事の大役を終えて人生をリセットした人間が、オフの時間に楽しんでいた分野に全エネルギーを注ぎ込み、自己の充実とともに新たな社会貢献を果たした例として励みとなる。とはいえ、渡欧した日本の芸術家がなぜ1930年以降に激減するのかといった要因が、為替レートの大幅な変化、それ以前は日本円が過大評価されていたことを読み取ることができるのはバンカーだった著者ならではの重要な視点である。やはり、自己の特性を見つめた上で、第二の人生の楽しみを決める必要があろう。
いずれにしても、板倉鼎という画家とその周辺画家を調査した本書は、フォーヴィスムに影響を受けた里見勝蔵や佐伯祐三らよりも少し下の世代の表現の変化を紹介したものとして貴重である。
本書の中で特に可能性が感じられたのは、著者の作品解説である。たとえば、清水多嘉示という彫刻家であり画家が描いた女性像の表現をめぐっての記述はこうだ。
[ 裸体画だけに線は身体の輪郭を示すだけだが明瞭な一本の連続線ではない。左上の胸部と腹部を仕分けて二の腕から前腕を浮き出させる部分、左乳房内側の部分はノミの彫り残しの淵のようだ。筆触による面取りと橙一色の濃淡で肌の起伏を示し背景の暗緑色一色と相俟ってそれを補強している。 ]
これは著者が収集したコレクションに対する作品解説なので、実物に向き合いながら執筆できるという恵まれた環境にある。まるで絵を描いているかのように作品を観察して詳述する、著者の力を認めないわけにはいかないが、実物を前にして記述してみると、素敵な言葉が降ってくるときが誰にでもあるのではないかと思わせる、そんな可能性が感じられた。我々がコレクターでなければ、美術館に行って実物を前にして鉛筆でメモを取ればよいのである。
本書は板倉鼎が生きた同時代の画家にもスポットが当てられている。岡鹿之助はまだしも、佐分真、北島浅一、御厨純一に清水登之など、最近では美術館で展示される機会がずいぶんと減ったように思える。高度経済成長の波に乗って全国各地に生まれた美術館は、潤沢な予算のもとで地域ゆかりの作家の調査と顕彰が行われた。しかしながら当時は年間あたりの展覧会の本数も今の倍以上で多忙を極め、顕彰は十分にできたとは言えないなかで、現在は学芸員の世代交代が進み彼らの関心の対象が大きく変化している。世間でもファッション雑誌が取り上げるほどの格好良さげなアートがもてはやされている。この点を、美術の素養がありながらビジネスで世界を駆け巡った水谷氏が危惧され、本書のように形に残してくれたことが僕にとって何よりもうれしい。 (サイトウミュージアム学藝員)
(「コールサック」120号 2024年12月号掲載)